小規模不動産特定共同事業とクラウドファンディング─ESG時代の新しい不動産投資

日本の不動産市場は、かつての「都心一極集中型」から転換を迫られています。人口減少・少子高齢化が進む中、地方では空き家や遊休不動産が急増しており、シャッター街や古民家の放置など、地域の課題は深刻さを増しています。
一方、投資家にとっても都心部の不動産価格は高騰し、利回りは低下しており、従来型の不動産投資は、手の届きにくい存在になりつつあります。
こうした状況に新たな可能性を示しているのが、小規模不動産特定共同事業とクラウドファンディングを組み合わせた仕組みです。ESG投資やSDGsへの関心が高まる今、社会課題の解決と収益を両立させる「新しい不動産投資」として注目されています。
変わる不動産投資環境:地方・遊休不動産の台頭

かつて不動産投資といえば、都心のオフィスビルやマンションが主役でした。しかし近年は価格上昇により利回りが低下し、個人投資家には参入が容易ではなくなってきました。
その一方で、地方では「空き家問題」「遊休不動産の増加」が社会課題として浮上しています。人口減少に伴う需要減で、不動産価値が下落するケースも少なくありません。
しかし、そのような地方の遊休不動産は、再生・活用次第で資産価値を取り戻せるポテンシャルを秘めています。 つまり、地方の遊休不動産は「リスク」でもあり「新しい投資のチャンス」でもあるのです。
小規模不動産特定共同事業とは?─制度が開く新しい道
2017年の法改正により創設された小規模不動産特定共同事業は、不動産投資に大きな転換点をもたらしました。
従来の「不動産特定共同事業」は、資本金や体制面の基準が厳しく、中小事業者や地域事業者が参入しづらい状況でした。改正により事業への参入条件が緩和され、地方の事業者でも、空き家や古民家を対象に小規模な投資事業を組成できるようになったのです。
投資家にとっては、個人で投資するにはリスクのあった地方の遊休不動産物件を、プロの事業者が運営する1口100万円程度から出資可能な「不動産小口化商品」として投資ができるようになりました。事業者には情報開示義務や報告義務が課され、投資家保護の仕組みも整備されています。
この制度により、「大手資本でなければ動かせなかった不動産再生」が、中小規模でも実現可能になり、個人投資家の参入機会が広がりつつあります。
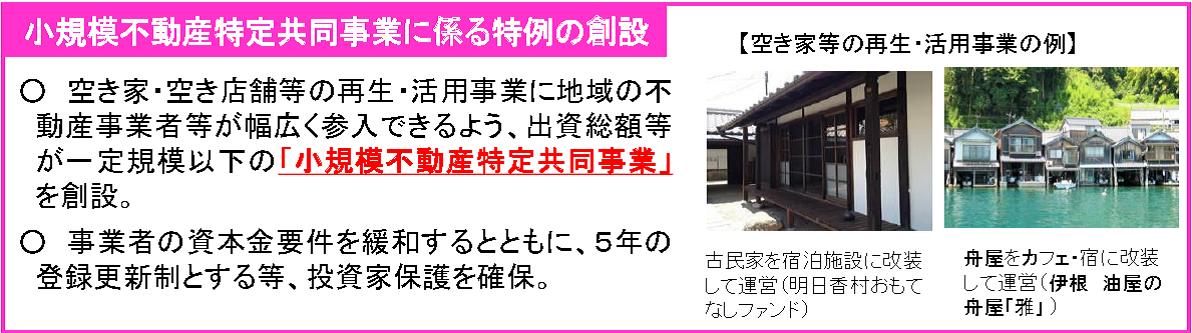
※国土交通省 公表資料抜粋
クラウドファンディングと不動産投資の関係
クラウドファンディングは、インターネットを通じて多数の人から少額ずつ資金を募る仕組みです。不動産分野では近年「不動産投資型クラウドファンディング」として広がりを見せています。
特に小規模不動産特定共同事業と組み合わせることで、投資家は「単なる資金提供者」ではなく、地域再生のストーリーに参加する一員となれます。これは従来の不動産投資にはない魅力です。
不動産投資型クラウドファンディングのメリット
不動産投資型クラウドファンディングは、主に以下のような特徴があります。
少額から始められ、手間なくプロに任せられる不動産投資というメリットだけでなく、流動性の低さや元本保証がないというデメリットもあります。
少額から投資できる
一口100万円程度から始められる案件が多く、従来の不動産投資のように数百万円〜数千万円の資金を必要としません。初期投資が少ないため、初心者や資産形成の入り口として取り組みやすいのが魅力です。
物件の運営はプロに任せられる
投資家は出資するだけで、物件の購入・管理・運営は事業者が代行します。入居者対応や物件の修繕対応などの手間も不要です。
投資対象は多様
マンション、アパート、商業施設、ホテル、再生不動産など幅広い案件が存在します。近年では、ESGや地域再生など「社会貢献型」のプロジェクトも増加しています。
透明性の高い情報開示
案件ごとに投資概要、想定利回り、運用期間、リスク説明が公開されるため、事前に比較・検討が可能です。
不動産型クラウドファンディングとESG投資の関係
ESG投資とは、E:環境(Environment)、S:社会(Social)、G:ガバナンス(Governance)の3つの観点から企業やプロジェクトを評価し、持続可能な社会づくりにつながる投資を行う考え方です。
不動産型クラウドファンディングは、ESG投資の3要素と自然に結びつきます。
| 投資型クラウドファンディングでの具体例 | |
|---|---|
| E:環境 (Environment) |
・省エネ建築やZEB(Net Zero Energy Building)の改修 ・老朽化物件の再生で廃棄物削減 |
| S:社会 (Social) |
・空き家・空き店舗を地域交流拠点や福祉施設に転用 ・地方創生や雇用創出につながる再生プロジェクト |
| G:ガバナンス (Governance) |
・不動産特定共同事業法に基づく運営 ・定期的な情報開示、収益報告、リスク説明の透明性 |
つまり、投資家は「利回り」を追求しつつ、「社会的意義あるプロジェクト」にも貢献できます。これはESG時代の投資家にとって大きな付加価値です。
ESG投資の特徴
ESG投資には以下の特徴があげられます。
●少額からESG投資
一口100万円程度から投資が可能
●社会的リターン+経済的リターン
賃料収入や売却益を得ながら地域活性化に参画
●分散投資が容易
複数の環境・地域系プロジェクトに分散して資金を分けられる
●環境(E)
古民家や空き家を再利用し、新築時の環境負荷を抑制
●社会(S)
地域活性化、雇用創出、コミュニティ再生
●ガバナンス(G)
法制度に基づいた透明性ある事業運営、投資家保護の仕組み
つまり、不動産型クラウドファンディングは、少額投資で、環境配慮や地域貢献をしながら収益を得る というESG投資の考え方に沿った手法です。
特に、空き家再生や地域活性化型のプロジェクトは、環境保全(E)・社会的課題解決(S)・透明な運営(G)を一度に実現できる注目分野です。
将来性と社会性を兼ね備えた投資を目指すなら、不動産型クラウドファンディングは有力な選択肢となります。
成功の鍵と留意点
魅力的なスキームである一方、注意すべき点も存在します。
物件の選定
地方の遊休不動産の再生や地域活性化のプロジェクトは、地域貢献という魅力も加わりますが、プロジェクトの事業計画や、人口動態、地域需要を的確に見極める必要があります。
流動性は限定的
市場でいつでも売買可能な株式やREITと異なり、運用期間中は途中解約できない商品も多くあるため、計画的な運用が必要です。
管理運営の体制
不動産は維持管理が欠かせず、体制不備はリスク要因となります。適切に運営管理を行う、透明性の高い信頼できる事業者を見極める必要があります。
リスクは分散されているが元本保証はない
小口で複数案件に分散しやすいためリスクヘッジが可能です。ただし、運営事業者の倒産や物件の収益悪化などによって、元本割れする可能性もあります。投資家保護のための優先劣後方式を採用する商品を選ぶなど、商品の見極めが大切です。
投資家は「社会性」に共感するだけでなく、リスクとリターンのバランスを見極める目を持つことが重要です。
展望と未来への期待
今後、地方創生や地域再生のプロジェクトにおいて、クラウドファンディングと小規模不動産特定共同事業はますます活用されるでしょう。自治体との連携、地域住民の参加、観光資源の再生など、多様な可能性があります。
投資家にとっても、単なる資産運用を超え、「自分の資金が社会を動かす」という実感を得られる点が大きな魅力です。
まとめ
不動産投資は「都会の大規模物件を資産家が買う」というかつてのスキームから、大きく多様化してきています。近年では、 地方の遊休不動産 × 小口投資 × クラウドファンディング × ESGという新しい形が広がりつつあります。
- 少額から参加できる
- 社会課題の解決に貢献できる
- 収益性と社会性の両立を目指せる
これらの要素を兼ね備えた「小規模不動産特定共同事業」は、これからの時代にふさわしい投資の一形態といえるでしょう。
あなたも資産運用の一歩を踏み出す際に、地域と未来をつなぐ投資を選択肢に加えてみませんか?
湘南ユーミーまちづくりコンソーシアムは、地域密着企業として湘南の地に根ざし、この地域でしか得られない不動産価値を創出するため、投資用アパート・マンションの開発・販売を手掛けています。
湘南の地に人々が集うことで、豊かな暮らしを育むためのビジネスが生まれ、経済が活性化していく。このように、不動産事業を通じて湘南の発展と新たな価値の創造に寄与してまいりました。
土地の有効活用から賃貸経営、不動産小口化投資、将来を見据えた売却や節税対策にいたるまで、資産形成だけにとどまらない、まちづくりに貢献・参加できる意義のある不動産投資をご提案いたします。
湘南地域の不動産投資に関するご相談は、全てお任せください。











