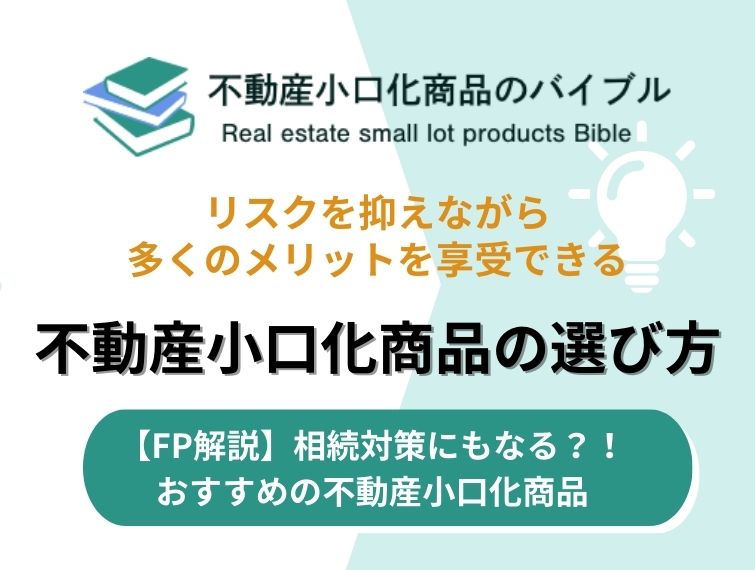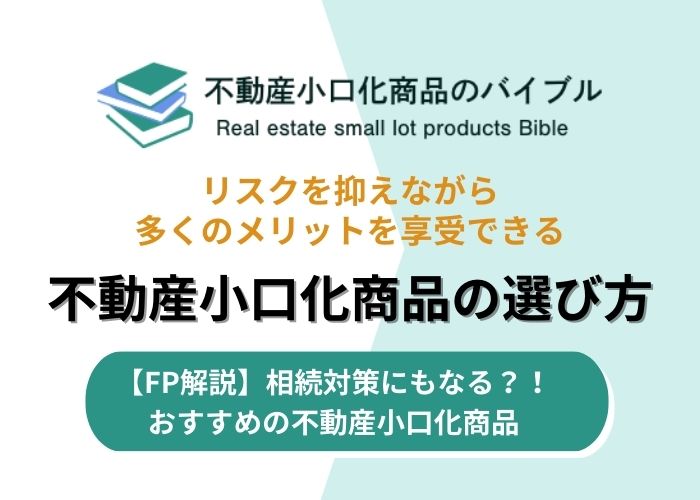みんなで大家さん」行政処分から学ぶ!リスクを抑えた商品の選び方

不動産小口化商品は、少額から始められる不動産投資として人気を集めています。
しかし最近「みんなで大家さん」に対する行政処分のニュースを見て「不動産小口化商品は危険なのでは?」と感じた方もいるかもしれません。
本来、不動産小口化商品は安定した賃料収入を得られる「リスクを極力抑えた商品」であり、投資家保護の仕組みも備わっています。それにもかかわらず、開発中物件などリスクの高い商品を選んでしまうことで、思わぬ損失につながるケースもあります。つまり、危険なのは不動産小口化商品そのものではなく、収益性の根拠が不透明なケースや法令遵守なされていないケースであるという点です。
この記事では、2024年に下された「みんなで大家さん」行政処分の事例を踏まえて「危険な不動産小口化商品の見極め方」をわかりやすく解説します。
不動産小口化商品の安全性

「不動産小口化商品」とは、1つの不動産を複数の投資家で共有し、それぞれが持分に応じて賃料収入や売却益を得る仕組みです。
株式や投資信託と同様に元本保証はありませんが、まずは不動産小口化商品にはどのような投資家保護の仕組みがあるのかを確認してみましょう。
優先劣後構造
多くの不動産小口化商品(特に匿名組合型の商品やクラウドファンディング)で採用されている、投資家の元本割れリスクを大きく軽減する仕組みです。
万が一、不動産の価値が下落し、損失が発生した場合は、まず劣後出資者である運営会社の出資分から先に損失が補填されます。劣後出資分の範囲内であれば、投資家の元本は守られることになります。
法規制と事業者の信頼性
不動産小口化商品を扱う事業者は、不動産特定共同事業法(不特法)に基づき、国土交通大臣または都道府県知事の許可・登録が必要です。この許可基準には、資金面や管理体制に関する要件が含まれており、一定の信頼性の担保となります。
マスターリース契約(一括借り上げ)
多くの小口化商品において、運営会社(または関連会社)が物件の賃貸管理を担い、物件全体を一括で借り上げる契約を結びます。これにより、一定の賃料収入が確保され、投資家への分配金の安定性が高まります。
厳選された投資対象物件
収益の安定性を重視し、都心や駅近など、好立地で賃貸需要が高く、資産価値が安定しやすい物件が選定され、オフィス、レジデンス(住居)、商業施設、物流施設など、経済情勢や需要の変化に強い用途の物件が選ばれます。
これらの仕組みにより、不動産小口化商品は、現物不動産投資に比べて手間がかからず、かつリスクを低減しつつ安定したインカムゲインを期待できる商品構造となっています。
なぜ「みんなで大家さん」は問題となったのか?

本来は、少額で不動産の安定収益を得られる仕組みとして注目されている不動産小口化商品ですが、2024年6月不動産小口化商品「みんなで大家さん」の運営・販売会社が、不動産特定共同事業法に基づき、東京都と大阪府から業務の一部停止命令を含む行政処分を受けました。
「みんなで大家さん」の行政処分の理由は、以下の3点です。
1. 開発計画の重大な変更に関する説明義務違反
これは、投資対象である「シリーズ成田」というプロジェクトで発生した、最も重大な違反行為の一つです。
開発計画が当初の予定から大幅に変更されたにもかかわらず、その変更が投資対象不動産の資産価値や将来的な収益性に与える影響について、運営会社が投資家に対し適切かつ十分に説明する義務を果たしませんでした。
不特法では、投資家の判断に影響を及ぼす重要な事項に変更が生じた場合、事業者は速やかにその内容と影響を説明しなければなりません。この説明が不十分であったため、投資家は自身が投資したプロジェクトの正確な状況や、それに伴うリスク増大を理解できないままになっていました。
2. 誤った情報に基づく勧誘・契約の進行
2点目は、契約の前提となる不動産の正確な情報を提供しなかった点です。
一部のファンドにおいて、本来は開発許可の対象ではない土地を誤って契約書類に記載し、その誤った情報を基に投資家への勧誘や契約締結を進めました。さらに、この誤りを是正するために土地の交換などを試みた際にも、投資家との契約変更に関する手続きが不適切であったと指摘されています。
投資家は、事業者が提供した書類上の情報を信用して投資判断を下します。この情報が事実と異なっていたことは、投資家を欺く行為であり、公正な取引を害する行為として不特法違反にあたります。
3. 契約成立前交付書面への記載不備
3点目は、投資家が契約前に受け取るべき重要書類(契約成立前交付書面)の内容が、法令の要求水準を満たしていなかった点です。
契約成立前交付書面には、特に開発プロジェクトの場合、「宅地造成工事完了時における土地の形状、構造等」を具体的に記載することが義務付けられています。しかし、同社の書面では、工事完了後の形状や構造を記載すべきところ、工事完了前の形状を記載するなど、不正確または不十分な記載が見られました。
開発物件の最終的な形状や構造は、その物件の資産価値や利用可能性に直結する極めて重要な情報です。この記載が不適切であったことは、投資家が正確な情報に基づいて投資を決定する機会を奪ったと判断されました。特に、対象不動産に接する道路の構造や幅員など、具体的な情報が不足していた点も指摘されています。
2013年にも業務停止命令の背景がある
「みんなで大家さん」は2013年にも、配当金支払い遅延や不適切な資金管理を理由に6ヶ月間の業務停止命令を受けており、同社に対する市場や投資家の潜在的な不信感があった背景があります。
2013年には資金管理や配当の面で課題が指摘されたこともありましたが、2024年の処分では、情報開示や説明義務に関する点が中心となりました。
この事例からは、法令遵守や情報開示体制の継続的な見直しが、事業運営においていかに重要であるかが改めて浮き彫りになったといえます。
今回の行政処分は、開発型物件など将来の収益性に不確実性が伴う案件において、情報開示や説明の在り方が改めて問われた事例といえます。
つまり、不動産の収益構造を無視し、投資家保護の観点を欠いた設計こそが危険なのです。
行政処分は「みんなで大家さん」だけではない?

「みんなで大家さん」だけではなく、過去には不動産特定共同事業法(不特法)に基づく行政指導や処分を受けた事例が公表されています。
具体的な事例は、個々の自治体(都道府県)によって公表されていますが、違反の内容として多い傾向にあるのは、「みんなで大家さん」の事例とも共通する以下の点です。
どのような点が問題になりやすいか
契約成立前交付書面等の記載不備・不適切表示
不動産の「工事完了時の形状・構造等」について、必要な情報が十分に記載されていない、または誤った情報が記載されているケース。投資家が適切な判断をするために重要な情報が欠けている点が問題とされます。
投資家への説明義務違反
事業計画の変更など、投資対象の不動産の価値や収益性に影響を与える重要な事項について、投資家に対して適切かつ十分に説明しなかった事例。
公正を害する行為
法令で定められた手続きや規定を守らず、投資家の利益を損なう、または損なうおそれのある行為をした事例。
不特法は投資家保護を目的としているため、これらの情報開示や説明に関する違反が行政処分の対象となります。
投資家保護の視点を踏まえて、収益構造を慎重に設計することが安全な投資の鍵となります。
安全か危険かの判断基準
行政処分の事例で得られる教訓から、危険な不動産小口化商品(不動産クラウドファンディングや不特法商品など)を見極めるための重要なポイントをまとめます。
行政処分は、主に情報開示の不適切さや説明義務違反によって発生しています。したがって、信頼性を判断するには、これらの情報がどれだけ透明性を持って適切に開示されているかが鍵になります。
以下のポイントを参考に、複数の商品を比較し、納得できる情報開示と信頼性を持つ事業者を選ぶことが、危険な不動産小口化商品への投資を回避する第一歩となります。
1. 運営会社(事業者)の信頼性・透明性を徹底的にチェックする
| チェックポイント | 行政処分事例から学ぶリスク |
| 許認可の有無と種類 | 「不動産特定共同事業」の登録があるか、その登録番号(知事または大臣)を公式サイトや公的情報で確認する。無登録や行政処分歴がある場合は要注意。 |
| 行政処分・トラブル歴 | 過去に業務停止、業務改善命令、配当遅延、元本毀損などの行政処分やトラブルがないかを検索などで確認する。繰り返しの処分はガバナンスに問題がある可能性が高い。 |
| 情報開示の透明性 | 会社の財務状況(親会社・グループ会社の信用力含む)過去の実績(償還率、配当実績)を積極的に開示しているか。開示が不十分な会社はリスクが高い。 |
2. 投資対象物件と計画の具体性を確認する
| チェックポイント | 行政処分事例から学ぶリスク |
| 事業計画の具体性 | 「開発計画」の場合、計画の変更リスクがある。具体的な開発許可の状況、工事の進捗、完了後の形状・構造などが「契約成立前交付書面」で詳細かつ正確に記載されているかを確認する。 |
| 利回り・収益の根拠 | 相場からかけ離れた高すぎる利回りを謳っていないか。その利回りがどのような計算(家賃収入、売却想定価格など)に基づいているか、根拠が明確かを確認する。 |
| 物件情報の詳細 | 物件の所在地、築年数、稼働率、賃料水準など、客観的な情報が十分に開示されているか。「ほぼ更地」など、実態と異なる情報がないか、可能な限り裏付けを取る。 |
| リスクに対する説明 | 物件特有のリスク(空室、賃料下落、売却価格下落など)が隠されず説明されているか。リスクを過小評価するような断定的表現を使っていないか。 |
3. 投資家保護の仕組みを確認する
| チェックポイント | 目的 |
| 優先劣後出資 | 損失が発生した場合に、まず運営会社が出資している劣後部分から負担する仕組みがあるか確認する。この比率が高いほど、投資家の元本保護の安全性は高まる。 |
| マスターリース(サブリース)契約 | 運営会社が物件を一括で借り上げ、空室の有無にかかわらず一定の賃料を保証する仕組み(契約内容を要確認)。分配金の安定性につながる。 |
| 流動性(途中解約) | 途中解約の条件や手続き、過去の実績を確認する。行政処分後に解約が一時停止された事例もある。 |
完成済み・賃貸中物件は安定性が高い
安定性を重視するなら、やはり完成済みで賃貸中の物件を対象とした商品が理想です。
入居者がすでに確保されているため、家賃収入という実際のキャッシュフローに基づいて分配されます。
安定性の高い不動産小口化商品を見極めるには、次の点を確認しましょう。
●物件が完成済みで稼働中(賃貸中)である
●分配金が家賃収入を原資としている
●テナント情報・契約期間・入居率などのデータが開示されている
●運営会社が小規模不動産特定共同事業法の登録事業者である
これらが明確に示されていれば、実物不動産投資と同じように安定した運用が期待できます。
高利回りに潜むリスクを見抜く
不動産投資をするにあたり「利回り」は重要な指標ですが、不動産小口化商品で年利8〜10%以上のような商品には注意が必要です。
不動産小口化商品は、1棟物件に比べて利回りは低くなります。堅実な賃貸経営で得られる不動産小口化商品の利回り(3〜5%前後)を大きく超える場合は、開発リスクや立地の不確実性を織り込んだものである場合がありますので注意が必要です。
「利回りが高い=良い商品」ではなく、リスクとリターンのバランスを見極めることが重要です。
リスク分散型の不動産運用として小口化商品を選ぶメリット
不動産小口化商品は、危険を避けて正しく選べば、次のようなメリットがあります。
- 分散投資:複数物件に少額ずつ投資でき、エリア・用途リスクを軽減
- 相続対策:持分単位で贈与・相続が可能
- 管理負担の軽減:運営・管理を事業者に委託できる
不動産投資の第一歩として不動産小口化商品を検討している方はもちろん、これまで1棟所有で集中リスクを抱えていた不動産オーナーにとっても、小口化商品は「リスク分散型の不動産運用」として有効な選択肢になり得ます。
まとめ|不動産小口化商品は、投資家と業界が共に育てる
「不動産小口化商品は危険なのでは」というイメージの背景には、行政処分などのニュースが影響しています。
しかし、不動産小口化商品の取引は、本来ならば各種法令等による規制の下、リスクを極力抑えた投資商品です。
2024年に「みんなの大家さん」に下された行政処分は、事業者にとって法令遵守(コンプライアンス)はもちろんのこと、投資家に対して「いかに誠実に、透明性高く情報開示を行うか」改めて問われることになりました。
このような事例を鑑みて、投資家の皆様も、高い利回りという「結果」だけを追い求めるのではなく、その「プロセス(=事業者の信頼性やスキームの安全性)」を厳しく見極めるリテラシーを向上させる必要があります。
事業者の透明性を高める努力と、投資家の成熟した選択眼。その両輪が揃って初めて、不動産小口化商品は真に信頼される資産形成の手段となると言えるでしょう。
▶湘南ユーミーまちづくりコンソーシアムの不動産小口化商品はこちら